親が亡くなった、または施設に入ったあと、誰も住まなくなった実家をどうするか――。
多くの人が直面するのが「実家じまい」です。
しかし実際に進めようとすると、「何から始めるべき?」「いくらかかるの?」といった疑問や不安が押し寄せてきます。
この記事では、実家じまいにかかる費用の総額を明確にし、その内訳や費用を抑えるコツ、実際のシミュレーション事例まで詳しく解説します。
✅ 費用を抑えるための工夫
✅ 解体や遺品整理の相場
✅ 相続登記や税金のポイント
など、初めての実家じまいでも安心して準備が進められる内容をわかりやすくまとめています。
この記事を読むことで、自分の場合はいくらかかりそうか、どんな選択肢があるのかが見えてくるはずです。
実家じまいにかかる費用の総額はいくら?【初めての人向けガイド】
実家じまいとは、親が住んでいた実家を整理・売却・解体・管理から解放する一連のプロセスを指します。高齢の親が亡くなった後や、施設へ移るタイミングで必要になることが多く、想像以上に手間も費用もかかるのが実情です。
✅ 実家じまいの総費用は、平均で50万円〜300万円程度が相場です。ただし、家の状態や所有者の対応状況によって、これ以上に膨らむことも少なくありません。
費用の内訳は、主に以下のような作業から成り立っています。
- 遺品整理や不用品回収
- 清掃・ハウスクリーニング
- 解体工事(必要に応じて)
- 相続手続き・名義変更
- 固定資産税や管理費の清算
- 売却または賃貸にかかる仲介手数料
多くの人が「実家を片付けるだけだからそれほどかからないだろう」と考えがちですが、想定外のコストが次々と発生しやすい点が注意ポイントです。とくに、ゴミ屋敷化していたり、長年空き家になっていた場合は費用が倍以上に膨らむケースもあります。
初めて実家じまいを行う人にとっては、総額の見積もりを早い段階で出しておくことが非常に重要です。見積もりを取らずに進めてしまうと、予算オーバーや手続きの遅れで大きなストレスを抱えることになります。
実家じまいにかかる費用の総額はいくら?【初めての人向けガイド】
実家じまいとは?費用が発生する背景と主な作業内容
実家じまいとは、親の死去や介護施設への入所などをきっかけに、住まなくなった実家を整理・処分・管理終了させる一連のプロセスを指します。
一見「片付けるだけ」と思われがちですが、実際には多くの作業と費用が発生します。
✅主な作業内容は以下のとおりです。
- 遺品整理・不用品の回収
- 清掃(ハウスクリーニング)やリフォーム
- 実家の売却・解体・更地化
- 相続登記・名義変更の手続き
- 空き家管理の終了・税金清算
これらを家族だけで完了させるのは困難で、専門業者の手を借りる場面が多いため、費用がかかるのです。しかも、感情的な負担が大きく、手続きが煩雑なため、十分な準備と計画が求められます。
実家じまいにかかる費用の総額を事前に把握すべき理由
実家じまいは、思い立ってすぐにできるものではありません。作業の順序や関係機関との調整、法的な手続きが複雑であるため、費用の全体像を把握しておくことが成功のカギになります。
✅費用を事前に把握すべき理由は以下のとおりです。
- 業者に頼んだときの見積もり比較がしやすくなる
- 想定外の出費(相続手続き・残置物処理)を防げる
- 節約できるポイントを計画的に選べる
- 相続人間でのトラブルを避けられる
特に遺産分割協議が必要な場合や、空き家の売却・活用を考えている場合は、事前の資金計画がないと、トラブルや時間的ロスが生じやすいです。
実家の規模・状態によって費用総額が大きく変わる
実家じまいにかかる費用は、家の広さ・築年数・立地・汚れ具合などによって大きく変動します。
以下のような条件が費用を左右します。
| 条件 | 費用が増える要因の例 |
|---|---|
| 広さ・間取り | 部屋数が多いほど、整理・清掃コストが増加 |
| ゴミの量・状態 | ゴミ屋敷・大量の不用品があると高額に |
| 立地(交通の便) | 山間部や過疎地では業者費用が高くなりがち |
| 建物の老朽化・破損 | 解体やリフォーム費用が必要になることも |
✅ たとえば、一軒家の3LDKで状態が良ければ100万円前後で済むこともありますが、築50年の老朽家屋で大量の遺品が残っていれば300万円以上かかるケースもあります。
つまり、「うちはそんなに汚れてないから大丈夫」と油断せず、実際の状況をもとに試算しておくことが重要です。
実家じまいの費用総額を構成する内訳【項目別に詳しく解説】
遺品整理・不用品回収費用の相場と注意点
実家じまいの中で最も初期に発生するのが、遺品整理と不用品の処分です。遺品の量や分別の有無によって、費用は大きく異なります。
✅ 一般的な相場は以下の通りです。
| 間取り | 費用相場(目安) | 内容の一例 |
|---|---|---|
| 1K〜1DK | 約3万〜8万円 | 家電・衣類・家具の回収 |
| 2DK〜3LDK | 約10万〜30万円 | 複数部屋の整理、貴重品仕分けなど |
| 一軒家(4LDK〜) | 30万〜80万円以上 | 倉庫・納屋も含む場合はさらに高額に |
注意すべきは、「遺品整理=ただのゴミ処分」ではないという点です。貴重品や権利書、写真など大切な物の仕分けには時間と人手がかかります。また、処分方法にも自治体の規制があり、違反すれば別途費用や罰則が発生することもあります。
プロの遺品整理業者に依頼することで、作業がスムーズになる一方、複数業者から相見積もりを取ることがコストダウンの鍵です。
ハウスクリーニングやリフォームにかかる費用
遺品や不用品を処分したあとは、室内の清掃や必要な修繕を行います。特に長年放置されていた実家では、カビや汚れ、傷みが目立ち、通常の清掃では対応しきれないケースもあります。
✅ 清掃・修繕にかかる費用の目安
| 項目 | 費用相場(目安) | 内容 |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング | 3万〜15万円程度 | キッチン、浴室、トイレの徹底清掃など |
| 簡易リフォーム | 10万〜50万円程度 | クロス張替え、床補修など |
| 本格的なリフォーム | 50万円〜 | 水回り交換、屋根・外壁の補修など |
特に賃貸や売却を視野に入れている場合、リフォームの質が価格に直結します。逆に、売却前提であれば、必要最小限のクリーニングで済ませるのも費用を抑える一手です。
解体費用の目安と工事内容のポイント
築年数の古い実家や、倒壊リスクのある空き家は、解体して更地にするケースも多く見られます。
特に、売却希望者の中には「解体後のほうが土地が売りやすい」と判断する人もいます。
✅ 解体費用の相場は以下の通りです。
| 建物の構造 | 費用相場(1坪あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 木造住宅 | 約3万〜5万円 | 一般的な戸建住宅 |
| 鉄骨造・コンクリート造 | 約5万〜8万円 | 重機や手作業が必要になる |
| アスベスト含有建材あり | 追加で数十万円〜 | 特別な処理費用が発生することも |
その他、解体前に必要な電気・水道・ガスの停止手続きや、近隣住民への説明も費用と労力がかかる要素です。事前に施工業者とよく相談し、必要な届出や費用を明確にしておきましょう。
固定資産税・管理費などランニングコストも忘れずに
実家が空き家の状態で放置されている間にも、税金や管理費などのコストは毎年発生します。
すぐに実家じまいができない場合、これらの費用も考慮しておく必要があります。
✅ 代表的なランニングコストの例
- 固定資産税:年間10万円〜30万円前後(地域・建物評価による)
- 空き家の見回りや清掃代行:月1〜2万円
- 草刈り・雪かき・防犯対策:年数万円単位の出費になることも
放置期間が長引けば、これらのコストがトータルで数十万円規模に膨らむため、早めに方向性(売却・解体・賃貸)を決めることが経済的にも有利です。
相続登記・名義変更にかかる費用(司法書士報酬含む)
実家じまいを進めるうえで、避けて通れないのが相続手続きと登記の名義変更です。
この作業を怠ると、売却や解体が進められず、後々トラブルの原因になります。
✅ 登記・相続関連費用の目安
| 項目 | 費用目安(概算) | 内容 |
|---|---|---|
| 相続登記の登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% | 法務局に支払う税金 |
| 司法書士報酬 | 約5万〜10万円 | 書類作成・登記申請手続きなど |
| その他必要書類取得費 | 約1万〜3万円 | 戸籍謄本、住民票の写しなどの取得費用 |
2024年4月から相続登記の義務化が始まっており、怠ると過料(罰金)の対象になるため要注意です。
費用だけでなく、期限と手続きの流れも事前に確認しておきましょう。
費用総額のシミュレーション事例【金額感がひと目でわかる!】
一軒家を実家じまいした場合の費用総額例
一戸建て住宅を実家じまいする場合、築年数や立地、家の状態によって費用に大きな幅があります。
ここでは、標準的なケースを想定した費用例を見てみましょう。
✅ 一軒家(3LDK・築40年・都市部)の実家じまい例
| 項目 | 費用の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 遺品整理・不用品回収 | 約25万円 | 家具・家電・雑貨類が多い場合 |
| ハウスクリーニング | 約8万円 | 水回りを中心に全体清掃 |
| 解体費用 | 約120万円 | 木造住宅・約30坪 |
| 相続登記(司法書士費用含む) | 約10万円 | 登録免許税・書類取得費込み |
| ランニングコスト(2年分) | 約20万円 | 税金・草刈り・簡易管理含む |
| 総額 | 約183万円 |
このように、標準的な実家じまいでも180万円前後かかる可能性があることが分かります。
状態が悪化していたり、解体が不要だったりする場合は、この総額が上下します。
マンションの場合にかかる実家じまい費用の目安
マンションの実家じまいでは、解体費用は不要なものの、管理規約に従った対応や修繕費の精算が必要になる場合があります。
✅ マンション(2LDK・築30年)の費用イメージ
| 項目 | 費用の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 遺品整理・不用品回収 | 約15万円 | エレベーター使用・運搬費あり |
| ハウスクリーニング | 約5万円 | キッチン・浴室中心 |
| 相続登記 | 約8万円 | 登録免許税含む |
| 管理費・修繕費の精算 | 約3万円 | 売却前に精算が必要 |
| ランニングコスト(1年分) | 約10万円 | 管理費・税金など |
| 総額 | 約41万円 | 解体不要なぶんコスト抑制可 |
一軒家に比べて費用が抑えられる傾向にありますが、遺品の運搬や管理組合との調整が必要なため、対応に手間がかかることがあります。
実際にかかった費用事例:200万円以内で済んだケース
仮想の事例ですが、以下のようなケースで約190万円で実家じまいを完了した実例を紹介します。
✅ ケース概要
- 一戸建て、築45年、延べ床面積35坪、地方都市
- 遺族が一部作業を自分で実施し、業者と分担
- 解体後に土地売却を予定
✅ 実際の費用内訳
| 項目 | 実費用 | 節約ポイント |
|---|---|---|
| 遺品整理・ゴミ回収(業者) | 18万円 | 貴重品の仕分けは自力で対応 |
| ハウスクリーニング | 6万円 | 水回りのみ業者に依頼 |
| 解体工事(木造2階建て) | 115万円 | 近隣あいさつ含め対応がスムーズに |
| 登記・相続関連手続き(司法書士) | 9万円 | 書類準備を家族で協力して実施 |
| 空き家管理費(1年間) | 12万円 | 管理会社に月1回の見回りを依頼 |
| 合計 | 約190万円 |
このように、工夫次第で200万円以内に収めることも可能です。
ただし、体力的・時間的に無理のない範囲で自分で行うことが大切です。
実家じまいの費用を抑えるためのポイントとコツ
自分でできる作業とプロに任せるべき作業の分け方
実家じまいの費用を抑えるうえで最も効果的なのが、「どこまで自分で対応できるか」を見極めることです。
すべて業者任せにすると費用は膨らみがちですが、逆に全てを自力で行おうとすると時間も労力も大きくなり、結果的に手間がコストに変わってしまいます。
✅ 自分で対応しやすい作業
- アルバムや書類などの貴重品の仕分け
- 衣類・雑貨など一般ごみの分別と処分
- 市町村の粗大ゴミ回収を利用した大型家具の処理
- 電気・水道・ガスの契約解約手続き
✅ プロに任せた方が良い作業
- 大量の遺品・特殊清掃(汚れ・臭気が強い場合)
- 解体や不用品回収など重機や許可が必要な作業
- 相続登記や売却などの法的手続き
ポイントは「人手がかかるが単純な作業」は自分で、「専門性が高くてリスクがある作業」は業者に任せることです。
補助金・助成金制度を活用して費用を軽減する方法
地域によっては、空き家対策の一環として解体費や改修費に対する補助金・助成制度が用意されていることがあります。
これらを活用すれば、数十万円規模の節約が可能になることも。
✅ 活用できる主な制度(例)
| 補助金・制度名 | 対象内容 | 支援額の目安 |
|---|---|---|
| 空き家解体補助金 | 老朽化した空き家の解体費用 | 上限50万円〜100万円 |
| 空き家活用リフォーム支援 | 改修して賃貸・活用する場合の費用補助 | 上限30万〜50万円 |
| 相続登記支援制度(自治体) | 登記手続きの書類作成・相談支援 | 実費無料〜低額 |
補助金は条件が細かく、申請前に工事を始めると対象外になるケースが多いため、必ず事前に自治体に確認を取りましょう。
見積もり比較で損しない!業者選びの注意点
同じ作業内容でも、業者によって費用や対応に大きな差があるのが実家じまい業界の特徴です。
適正価格で納得のいくサービスを受けるには、複数業者からの相見積もりが基本です。
✅ 業者選びで注目すべきポイント
- 料金が明朗かどうか(追加費用の有無を確認)
- 作業内容が具体的に説明されているか
- 許可証や資格の有無(一般廃棄物収集運搬業など)
- 口コミや評判のチェック
また、最近では「実家じまいパック」などの一括サービスを提供する業者も増えており、個別に頼むより割安になる場合があります。
ただし、パックの内容をよく確認し、不要なサービスが含まれていないかをチェックすることが大切です。
実家じまいの費用に関するよくある質問Q&A
実家じまいの費用はいつ・どうやって支払う?
実家じまいにかかる費用の支払いタイミングは、依頼する業者やサービス内容によって異なりますが、一般的には以下のような形が多く見られます。
✅ 支払いタイミングの一般的なパターン
- 作業完了後の一括支払い(最も一般的)
- 一部前払い+残額後払い(高額な解体工事など)
- 着手前の見積もり時に内金が必要なケースもあり
支払い方法は、現金・銀行振込・クレジットカード対応など業者によって柔軟に対応しているところもあります。
ただし、見積書に明記されていない費用を後から請求されるトラブルもあるため、契約前に「総額いくらになるか」「追加費用の条件は何か」を必ず確認するようにしましょう。
また、司法書士など士業への支払いは、業務開始時に前払いを求められることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
支払った費用は相続財産から出せる?
実家じまいにかかる費用を、親が残した相続財産から支払うことは原則として可能です。
ただし、法的には相続人全員の同意が必要である点に注意が必要です。
✅ よくあるケース
- 代表相続人が立て替えて支払い → 後から相続財産で清算
- 遺産分割協議で「実家じまい費用を共通支出」として合意
相続人が複数いる場合は、費用負担をめぐって揉める原因にもなりやすいため、あらかじめ実家じまいに必要な費用の見積もりを用意しておき、全員で合意形成しておくことが大切です。
また、相続財産に現金が少ない場合は、売却代金や解体後の土地売却益から補填するケースもあります。
親が残した借金があった場合の実家じまいはどうなる?
親に借金があった場合、その借金も相続対象になります。つまり、実家じまいの前に「相続するか放棄するか」の判断をする必要があります。
✅ 選択肢と注意点
- 相続を承認する場合:借金も資産もすべて引き継ぐ
- 相続放棄する場合:借金も資産も放棄(実家じまいも不可)
- 限定承認:資産の範囲内で借金を返済する(手続きが複雑)
もし親が残した借金が多く、実家の価値が低い場合は、相続放棄を検討することで無駄な実家じまい費用を回避できることもあります。
ただし、相続放棄は原則として「相続開始から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があるため、タイミングを逃さないことが重要です。
判断に迷う場合は、早めに司法書士や弁護士に相談するのが得策です。
この記事を書いた人

- 不動産のプロとして33年のキャリアを持ち、お客様に寄り添った最適なサービスをご提供することに情熱を注いでいます。アットホームな社風の中、有能なスタッフと共に日々研鑽に励み、お客様の人生に幸せをもたらすことが私の喜びです。
最新の投稿
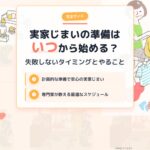 不動産売却物語2025年4月20日実家じまいの準備はいつから始める?失敗しないタイミングとやること完全ガイド
不動産売却物語2025年4月20日実家じまいの準備はいつから始める?失敗しないタイミングとやること完全ガイド 不動産売却物語2025年4月20日実家じまいの費用総額はいくら?内訳と節約術を事例で徹底解説!
不動産売却物語2025年4月20日実家じまいの費用総額はいくら?内訳と節約術を事例で徹底解説! 実家じまい2025年3月24日実家じまいの仏壇供養はどうする?魂抜きから処分まで徹底ガイド
実家じまい2025年3月24日実家じまいの仏壇供養はどうする?魂抜きから処分まで徹底ガイド 実家じまい2025年3月24日実家じまい手続きに必要な書類まとめ|相続・不動産売却・不用品処分のポイントも解説
実家じまい2025年3月24日実家じまい手続きに必要な書類まとめ|相続・不動産売却・不用品処分のポイントも解説
.jpg)
