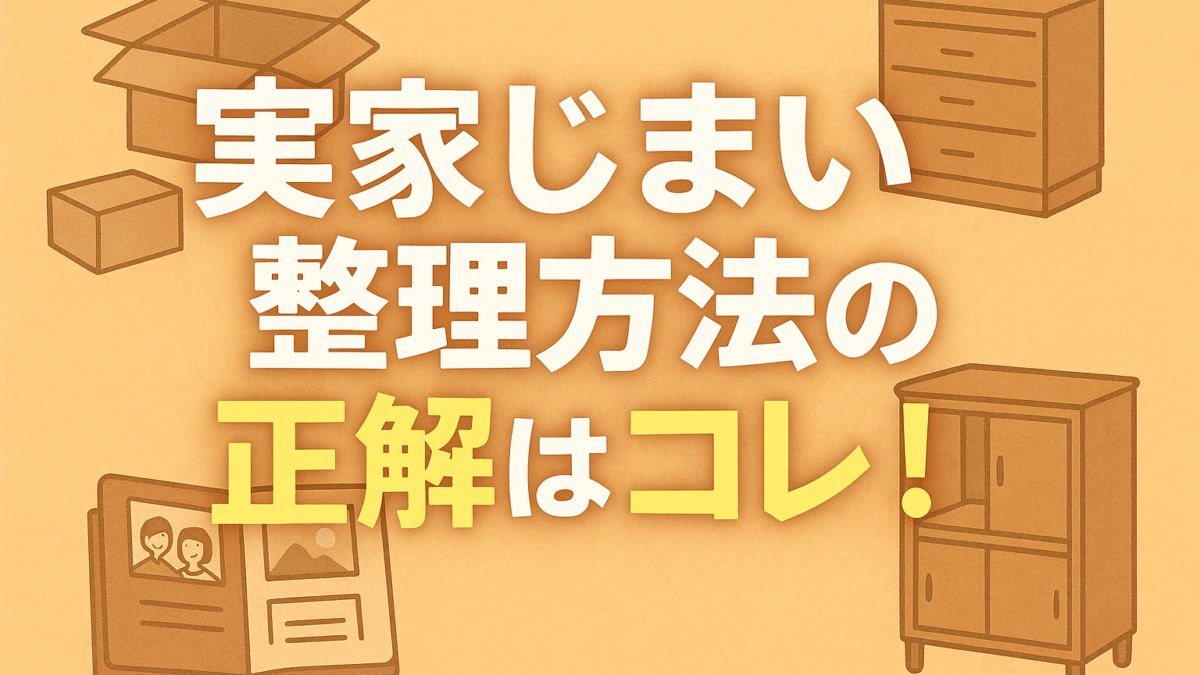実家じまいは、物の整理だけでなく気持ちの整理も必要な繊細な作業です。スムーズに進めるには、正しい手順と家族との連携がカギ。目次を見て必要なところから読んでみてください。
実家じまいの整理はどこから始める?【最初の一歩が大切】
実家じまいの整理は、多くの人が「どこから手をつけたらいいのかわからない」と感じる作業です。特に親の家には長年の思い出や家財道具が詰まっており、気持ちの整理と物の整理を同時に行わなければならないため、心理的なハードルも高くなりがちです。
ここでは、実家じまいをスムーズに始めるための第一歩として、整理が難航する原因と準備の進め方について詳しく解説します。
実家の整理が難航する原因と心理的ハードル
実家の片付けがスムーズに進まない理由の多くは、感情面の葛藤と物量の多さです。
✅ 感情的な要因
- 親との思い出が詰まった品を「捨てられない」
- 家族との話し合いがうまく進まない
- 実家ロスのような感情が先立ち、手が止まる
✅ 物理的な要因
- 年月とともに増えた家財道具・不用品が山積み
- 家中のタンスや押し入れ、クローゼットに物がぎっしり
- どこから手をつけるべきかの優先順位が不明
こうした理由から、「片付ける前に疲れてしまう」人も少なくありません。
特に思い出の品や写真アルバム、手紙などは「残すか捨てるか」判断が難しく、時間ばかりが過ぎてしまいがちです。
そこで必要なのが、片付けを始める前の準備と心構えです。
整理作業を始める前にやるべき準備と心構え
実家じまいを円滑に進めるためには、事前の段取りと家族との共有が成功の鍵となります。
以下に、整理作業を始める前に取り組んでおきたい項目を表にまとめました。
| 準備項目 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| ✅ 作業計画の立案 | スケジュールと担当者を決める | 日程を決めずに始めるとダラダラ続いてしまいます。小さなステップごとに計画を立てましょう。 |
| ✅ 家族会議 | 家族間で整理方針を共有 | 捨てる・残すの判断は、感情的な摩擦を生む可能性があります。あらかじめ共有を。 |
| ✅ 整理の優先順位決定 | 片付ける順番を決める | まずは使用頻度の低い部屋や納戸から手をつけるとスムーズです。 |
| ✅ 必要なツールの準備 | ゴミ袋・ラベリング用具など | 分別用ゴミ袋、マスキングテープ、マジック、収納ボックスは必須です。 |
準備段階では、「書類整理」や「遺品との違い」のように感情が関わりやすい項目からは避けるのがコツです。まずは「冷蔵庫の中身」「使用していない家電」など、判断しやすい不用品から取りかかるとスムーズに進みます。
また、心構えとしては以下のような意識を持つと良いでしょう。
- ✅ 完璧を目指さない
- ✅ 思い出を処分ではなく「保存」と捉える
- ✅ 必要なら専門業者や整理収納アドバイザーの助けを借りる
特に写真や手紙、仏壇や神棚などは、デジタル保存や供養サービスなどの選択肢もあります。プロの知見を借りることで、感情的な負担も軽くなるでしょう。
このように、実家じまいは心と物の両面の整理が必要です。段取りを整え、心の準備をしてから取りかかることで、途中で挫折するリスクを減らすことができます。
実家じまいの整理を効率よく進める5つのステップ
実家じまいは、単に「モノを捨てる」作業ではなく、感情や家族の記憶に向き合いながらのプロセスです。そのため、やみくもに片付け始めるのではなく、段階的なステップで整理していくことが重要です。
ここでは、実際に多くの人が実践して効果があった「5つの整理ステップ」をご紹介します。実家じまいの作業効率を上げたい方は、ぜひ参考にしてください。
ステップ①:家全体を把握し、整理の優先順位を決める
まず最初にやるべきことは、実家全体のボリューム感を把握することです。
いきなりタンスや押し入れの中を開けるのではなく、「何がどこにあるか」「どの部屋にどれだけモノがあるか」を把握しましょう。
✅チェックポイント:
- 家全体をざっと見て、片付けの対象となるエリアをリスト化
- 家族での話し合いで「優先的に整理すべき場所」を決定
- 高齢の親が使っていない部屋や納戸から始めると進めやすい
特に注意が必要なのが「実家の収納」や「仏壇・神棚」など、感情的な判断を伴うエリアです。これらは後回しにすることで、序盤のモチベーションを維持できます。
ステップ②:エリア別に小分けして作業計画を立てる
実家全体をいきなり片付けるのは非現実的です。そこで有効なのが、「部屋単位」や「収納単位」で小分けにして進める」というアプローチです。
| エリア | 優先度 | 解説 |
|---|---|---|
| 納戸・倉庫 | 高 | 使用頻度が低く、不用品の宝庫。判断しやすいモノが多く整理に向いています。 |
| キッチン | 中 | 食器やキッチン用品は数が多く、分類が大切。冷蔵庫の中身も忘れずに。 |
| 居間・リビング | 中〜低 | 思い出の品が集中しやすく、感情的になりやすいので注意。 |
| 押し入れ・クローゼット | 高 | 季節物や未使用の家電などが溜まりがち。優先的に整理すると達成感あり。 |
✅ 小さな範囲を一つひとつクリアしていくことで、整理作業がスムーズに進みます。
ステップ③:モノを「残す・手放す・迷う」に分類する
整理の基本は分類と仕分けです。ですが、実家じまいでは「捨てる・残す」の2択に絞ると判断に迷って作業が止まってしまいます。
そこでおすすめなのが、「残す・手放す・迷う」の3つに分ける方法です。
✅ ラベリングやマスキングテープを活用し、以下のように仕分けましょう:
- 残す(明確に必要・思い出として残したい)
- 手放す(不要と判断できる)
- 迷う(一時保留して再検討)
「迷う」に入れたものは一定期間保管して後で見直すことで、精神的な負担を軽減できます。写真アルバムや書類・契約書などは、スキャナーやスマホアプリでデジタル保存する選択肢も有効です。
ステップ④:不用品の処分方法を決めて手配する
分類が終わったら、次は不用品の処分です。ただし、自治体のゴミ回収だけでは処理しきれないものも多く存在します。
不用品の種類と処分方法を、以下にまとめました。
| 種類 | 処分方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 家電製品 | 粗大ゴミ/リサイクル回収 | テレビ・冷蔵庫などはリサイクル法に準拠 |
| 家具・家財 | 粗大ゴミ/不用品回収業者 | 解体や運搬が大変な場合は業者依頼が便利 |
| 衣類・布団 | 資源回収/処分 | 回収ボックスや寄付という選択肢もあり |
| 書類・契約書 | シュレッダー処理/溶解処理 | 個人情報保護の観点から安全に処分を |
| 仏壇・神棚・遺品 | 専門業者/お寺での供養 | 気持ちの区切りとして大切なプロセス |
✅ 大型の家具や家電が多い場合は、不用品回収業者の一括依頼が効率的です。プロの手を借りることで、時間も体力も大幅に節約できます。
ステップ⑤:残すモノの収納・保存を最適化する
不要なモノを処分したら、最後は「残すと決めたモノ」の収納と保管です。ここで重要なのが、ただしまうのではなく、今後の管理もしやすくしておくことです。
✅おすすめの整理術:
- 収納ボックスや引き出しにカテゴリ別にまとめて収納
- ラベリングして中身が一目でわかるようにする
- デジタルデータはクラウド保存や外付けHDDにバックアップ
写真や手紙、思い出の品は量を減らしつつ残す工夫を。どうしても捨てられない場合は、スキャナーで読み取り、デジタル化して保存するのがおすすめです。
このように、整理には時間も手間もかかりますが、進め方次第で効率も心の負担も大きく変わります。
整理作業をスムーズに進めるコツと実践テクニック
実家じまいの整理は、単に「片付ける」だけでなく、感情や思い出との向き合い方が問われる時間でもあります。だからこそ、無理なく、計画的に進めるテクニックを知っておくことが成功のカギです。
ここでは、感情的負担を減らしつつ、効率よく進めるための実践的なコツをご紹介します。
思い出の品や写真の整理に時間をかけすぎない工夫
実家じまいで多くの人がつまずくのが、写真アルバムや手紙、親との思い出の品です。見返しているうちに時間が過ぎ、作業が止まってしまうことも珍しくありません。
✅スムーズに整理するためのポイント:
- 「見る時間」を決める(例:1アイテムにつき1分まで)
- 後日整理用の「思い出ボックス」を作る
- 写真はスマホで撮影してデジタル保存し、物理的な保管を最小限に
- 大切な写真は、スキャナーやアプリを使ってデジタル化
「思い出が捨てられない」と感じるのは自然なことですが、作業を止めない工夫で前に進めます。
分別・仕分けがはかどるラベリングとチェックリスト活用法
実家の片付けでは、思った以上にモノの量と種類が多いのが現実です。途中で「これは何だっけ?」「これは誰のモノ?」と手が止まってしまうのは、分別と仕分けが曖昧な状態だからです。
✅そんな時に役立つのが、ラベリングとチェックリストの活用です。
| ツール | 活用方法 | 効果 |
|---|---|---|
| マスキングテープ | 箱や袋に「衣類」「写真」「書類」など分類名を書く | 中身が一目でわかるため、混乱を防止 |
| ラベルシール | 残す・捨てる・迷うの分類ごとに色分け | 視覚的に仕分けできるため、判断が早まる |
| チェックリスト | エリアごとに進捗を管理 | 作業の達成感を得やすく、継続しやすい |
✅チェックリストに「完了日」や「家族の確認欄」を加えると、家族会議の場でも活用できます。
見える化することで、感情に流されず整理作業が進めやすくなります。
1日で終わらせようとしない!時間を区切る整理術
「今日1日で終わらせる!」と意気込んでスタートし、結果的に疲れてしまい翌日以降に手がつかない——これは実家じまいでよくある失敗パターンです。
✅効率を上げるためには、「時間を区切って行う」整理術が有効です。
- 1回の作業は90分以内を目安に
- スマホのタイマーで作業時間をセット
- 終了後は達成感を感じられるように記録をつける
たとえば、「今日は押し入れ上段のみ」「キッチンの引き出し2段だけ」といったように、範囲を限定することが成功のポイントです。
また、整理収納アドバイザーや家事代行など、プロの手を一部取り入れることで作業スピードを格段に上げることも可能です。
✅整理は「一気に終わらせる」よりも、「継続できる形で行う」ことが大切です。
このように、実家じまいの整理方法には“心”と“技術”の両方が求められます。
整理する順番と場所の優先順位【実家じまい成功のカギ】
実家じまいにおける整理の成功は、片付ける順番とエリアの選定にかかっています。感情的にも体力的にも負担の大きい作業だからこそ、最初の段取りを間違えると全体がうまく進まなくなります。
ここでは、「どこから片付けるべきか?」という疑問に対して、実践的で失敗しにくい整理の優先順位を紹介します。
片付けにくい場所から手をつけない理由とは?
「まずは難しそうな場所からやってしまおう」と考える人も多いですが、実はそれが失敗のもとです。
✅整理の序盤に片付けない方がよい場所:
- 思い出の品が詰まった箱
- 写真アルバムや手紙の入った引き出し
- 仏壇・神棚周辺
- 親の私物が多く残る寝室
こうした場所は、感情的な葛藤が生まれやすく、思った以上に時間がかかる傾向があります。「思い出が捨てられない」という心理にとらわれてしまうと、手が止まり、モチベーションが下がる原因にもなります。
最初は“感情が絡みにくいエリア”から手をつけることで、整理のリズムを作りやすくなります。
キッチン・押し入れ・クローゼットから始めるのが鉄則
整理のスタート地点としておすすめなのは、使用頻度の高い日用品が多く、感情的ハードルの低いエリアです。具体的には以下の3箇所です。
| エリア | 理由 | 処分のポイント |
|---|---|---|
| キッチン | 消耗品・期限切れの食品など、感情が絡みにくい | 食器・調理器具は使っていないものから間引く |
| 押し入れ | 季節外の布団や衣類などが収納されており、判断がしやすい | 「1年以上使っていないもの」は不用品候補 |
| クローゼット | 衣類が中心で、分類・仕分けがしやすい | サイズや状態で仕分けし、「迷うゾーン」をつくらない |
✅さらに効率的に進めるには:
- ラベリングして中身を見える化
- 使用頻度の低いものから手を付ける
- 廃棄対象は不用品回収業者に依頼するのも有効
最初に達成感のある場所をクリアすることで、整理作業全体にポジティブなリズムが生まれます。
また、これらのエリアは他の家族との共有スペースになっていることも多いため、家族との話し合いがしやすいという点もメリットです。
✅感情的な負担を避けつつ、整理効率を最大化するには、「判断しやすい場所」から進めるのが鉄則です。
このように、整理のスタート地点と順番を見極めることで、実家じまいは確実にスムーズに進みます。
実家じまいに使える!整理アイテムと便利グッズ
実家の片付けをスムーズに進めるためには、適切な道具選びも大きなポイントです。心理的なハードルを下げるだけでなく、整理の進め方や作業効率にも影響するため、便利グッズの活用は非常に効果的です。
ここでは、「分類・仕分け」「処分準備」「思い出の保存」それぞれのシーンで役立つアイテムをご紹介します。
仕分け用の色分けシール・マスキングテープ
✅整理の初期段階で役立つのが、色で分類する方法です。とくに大量の家財道具を前にすると、「何をどこまで進めたのか」がわかりにくくなります。そんなときに活躍するのが色分けシールやマスキングテープです。
| アイテム | 用途 | 具体的な使い方 |
|---|---|---|
| カラフルな丸型シール | 仕分け分類(例:赤=処分、青=保管、黄=保留) | 箱や家具、家電に貼るだけで視認性が高くなる |
| マスキングテープ | ラベリングと補足メモ | テープに直接書き込みができ、貼り直しも簡単 |
視覚的に整理が進んでいる実感が得られるため、モチベーションの維持にも効果的です。
処分前に役立つ簡易工具・測定グッズ
✅家財道具の整理では、処分や運搬前の準備として、採寸や分解作業が必要になるケースがあります。
| グッズ | 役立つ場面 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| メジャー・巻尺 | 家具のサイズ測定、搬出ルート確認 | 処分業者に依頼する際にも必要になることが多い |
| ドライバーセット | 家具の解体 | 折りたたみ可能な工具は持ち運びにも便利 |
| 軍手・滑り止めグローブ | 安全な作業のために | 手を保護しながら、重い家具もつかみやすくなる |
安全かつ効率的な作業を支える必須アイテムとして、事前に準備しておくことをおすすめします。
写真・手紙のデジタル保存におすすめのスキャナー・アプリ
✅実家の片付けで最も悩ましいのが、「思い出の品」の扱いです。とくに写真アルバムや古い手紙などは捨てる勇気が持てないという人も多いでしょう。
そんな時に役立つのが、デジタル保存という選択肢です。
| ツール・アプリ | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 家庭用スキャナー | 高画質でスキャンできる | アルバムや古い書類も劣化せず保存可能 |
| スマホ用スキャンアプリ(例:Adobe Scan、Google フォトスキャン) | 手軽に取り込める | 外出先でも整理でき、家族と共有も簡単 |
「処分するか迷うもの」=「デジタル化して残す」という選択肢を持つことで、感情の整理と実物の処分を両立できます。
✅特に高齢の親や家族と整理を進める場合には、こうしたアイテムをうまく活用することで、感情的な摩擦を減らしつつ作業を進めることができます。
整理作業にかかる時間を大幅に短縮し、疲れやストレスを軽減するためにも、こうした便利グッズの導入は大きな助けとなるでしょう。
家族との協力で整理が進む!人間関係のコツ
実家じまいは、単に物を整理するだけではありません。家族の記憶や感情が深く関わる作業であり、ときには思わぬトラブルの火種になることもあります。円滑に進めるためには、家族との協力体制と共通認識が欠かせません。
ここでは、家族全員が納得しながら実家を整理していくための具体的な進め方をご紹介します。
整理方針を家族で共有するミーティングのすすめ
✅まず重要なのは、事前に家族全員で「整理のゴール」を共有することです。親の気持ちや兄弟姉妹の立場はそれぞれ異なるため、勝手に進めると後から大きな反発を招くこともあります。
以下のようなチェック項目を使って、事前の話し合いを行いましょう。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 整理の目的 | 実家を売却するのか、維持するのか |
| 作業の範囲 | どの部屋まで手を付けるのか、仏壇や神棚などはどうするか |
| 役割分担 | 誰がいつ何を担当するのか |
| 感情面の配慮 | 思い出の品や写真、親の意向にどう向き合うか |
事前の家族会議を「段取りのスタート地点」にすることで、後の作業が格段にスムーズになります。特に高齢の親が同席する場合は、親の気持ちを尊重する姿勢を忘れずに。
意見が割れたときの着地点の見つけ方
✅実家じまいでは、「捨てるか残すか」などの判断で意見が割れる場面が必ず出てきます。とくに思い出の品や親の遺したものに関しては、感情の衝突が起こりやすいポイントです。
そんな時は、以下の方法で冷静に着地点を探る工夫が有効です。
迷ったときの対処法リスト:
- ✅「保留ボックス」を設け、一旦判断を先送りにする
- ✅写真に撮ってから処分することで記憶を残す
- ✅デジタル保存で全員がアクセスできる状態にする
- ✅親や兄弟それぞれに希望を聞き、できる限り配慮する
- ✅必要であれば、第三者(整理収納アドバイザーなど)の助言を取り入れる
実際にあったケースでは、古いタンスの処分をめぐって兄弟が対立。そこで、タンスの写真を撮ってデジタルアルバムに残したところ、全員が納得して処分に踏み切れたという例もあります。
感情の整理=モノの整理にもつながるため、こうしたクッション的な工夫を取り入れてみてください。
家族との連携がうまくいくかどうかで、実家じまいの成功度は大きく変わります。トラブルを避けるためにも、感情に配慮した計画的な進行を心がけましょう。
✅「人間関係の整理」は、「物の整理」以上に重要なテーマかもしれません。
実家じまいの整理で起こりやすいトラブルとその対策
実家じまいは、「実家の片付け」や「家財道具の整理」など物理的な作業だけでなく、感情面や人間関係の調整も必要になる繊細なプロセスです。その中で、予期せぬトラブルが発生することは少なくありません。
ここでは、実家を整理する際にありがちな問題と、その具体的な対策を紹介します。
整理後に「捨てなきゃよかった」と後悔しないために
✅実家の整理でよくある後悔が、「思い出の品を勢いで捨ててしまった」というものです。これは特に、感情の整理ができていないまま片付けを急いだときに起こりがちです。
後悔を防ぐためのポイント:
| 工夫 | 解説 |
|---|---|
| 保留ボックスを用意 | 「迷うもの」はすぐに処分せず、一時的に保管して判断を後回しに |
| 写真や手紙はデジタル保存 | スキャナーやアプリを活用して、処分しても記録を残せるようにする |
| 家族にも確認を取る | 捨てる前に兄弟や親族に一言共有しておくことで、後のトラブルを防げる |
「捨てる勇気」も大切ですが、「残す覚悟」も必要です。時間的余裕があるなら、思い出の品にはワンクッション置いてから判断するのが賢明です。
無理に一人で抱え込まない!外部の手を借りるタイミング
✅整理を進めるうちに、荷物の多さや気力の限界から、「自力ではもう無理だ…」と感じる瞬間が来ることも。そんな時は、無理にすべてを自分でやろうとせず、専門業者や地域の支援サービスの活用を視野に入れましょう。
頼れる外部リソース:
- ✅ 不用品回収業者:家具や大型家電などの回収を一括で依頼できる
- ✅ 整理収納アドバイザーや遺品整理士:仕分けの段取りから心のケアまで対応
- ✅ 地域包括支援センターや市役所の相談窓口:高齢者サポートに関する情報提供
- ✅ 家事代行サービス:掃除や簡単な整理などのスポット依頼が可能
事例:70代の両親の家を整理していた方が、仏壇の扱いや冷蔵庫の処分に困り、専門の整理士に依頼したところ、「心の負担が半分以下になった」と語っています。
自分だけで完璧に進める必要はありません。むしろ、第三者のプロの手を借りることで、家族関係の摩擦を減らすこともできるのです。
✅実家じまいは、体力だけでなく心理的にも負担の大きいライフイベント。うまく外部の力を活用しながら、無理なく前に進めましょう。
この記事を書いた人

- アーキ君
最新の投稿
 スタッフブログ2025年7月31日【知らなきゃ損!瀬戸内市近辺で1日まるごと“おいしい”体験】
スタッフブログ2025年7月31日【知らなきゃ損!瀬戸内市近辺で1日まるごと“おいしい”体験】 お客様の声2025年7月21日御社は信頼・信用できましたので不安はありませんでした。
お客様の声2025年7月21日御社は信頼・信用できましたので不安はありませんでした。 お客様の声2025年7月21日なんでも相談できた。
お客様の声2025年7月21日なんでも相談できた。 お客様の声2025年7月1日色々と動いて下さり助かりました。
お客様の声2025年7月1日色々と動いて下さり助かりました。
.jpg)